日本林業再生の願い
先日、加盟しているウッドマイルズ研究会の総会が東京であり参加してきました。この会の目的は地産地消の木材を利用する事により木材運搬に関わるCO2削減を図ろうとするもので、その為に一般消費者にも分かりやすくその指標を公開しようとする研究会です。午前中に総会があり午後からはフォーラムが開かれ講師による講演や参加者による意見交換等が行われ活発な意見が交わされました。
しかし仕事柄、こういう会議や打ち合わせに参加する事が多いのですが今、日本の林業は本当に衰退してしまい、おまけに昨年来の経済危機が追い討ちをかけるように衰退に拍車をかけた格好で川上側となる山元の林業関係者は悲鳴を上げています。会議が行われる度に政治が悪い、工務店が悪い、林業家が悪いとお互いに中々どうしたら良いのかという議論に発展していかない位、疲弊した状況が続いています。
今、日本には国内で建築される木造住宅の全てを国産材で供給出来るだけの生産量があるのですが実際にはその大半を輸入材が占めている状況です。何故、このような不可思議なことになってしまったのか?色々なところで色々な意見があって私にもこれが原因だなんて事は分からないのですが最近、ひとつ感じるのは「文化の違い」と言う事です。
これだけ山林に囲まれた日本が森林文化に疎いなんて事は思いたくないのですが急速な経済発展やそれに伴う諸外国からの圧力が森林文化の発展を妨げてきたのではないかと思います。それは食料自給率の低下にも似た現象ではないかと思います。国内で充分な供給体制があるにも関わらずそれらの資源を生かせない仕組みや文化が築かれてしまったんではないでしょうか?
今の子供達が「近くに立っている木を倒して家にする」なんていう感覚を感じる事が出来ているのでしょうか?私にはすごく疑問です。子供の頃に海や川に行って魚を釣って自分で焼いて食べるなんていう体験がそういう文化の継承には絶対に必要だと思うのです。同じように木を切ってそれで物を造るなんて体験が森林文化を築くのだと思うんですよね。いまだに、里山つくりなんてイベントをお手伝いしていても「木を切るなんてとんでもない。それなら私は帰ります」なんて怒って帰られる方もいます。何をかいわんやですがその程度しか理解がないというのが実情なんです。
ではどうしたら良いか?それが分かればとっくに日本の林業は再生しているのですがその方法が分からないから苦しんでいるのです。私も仕事柄、木を扱うので山元の方の苦悩はいつも聞いています。その時に感じるのは「卵が先か鶏が先か」の疑問なんです。私は自分たちで使う良い木が欲しい、そういう木を伐り出して欲しい。山元の方はいつも大量に使ってくれるなら伐るけどそうでなければ伐るだけ赤字でやっていけない・・・いつもこの議論のどうどう巡りです。
良い木がないから注文出来ない。注文がないから伐らない。ではどうすれば???川下側の消費者が変わらなくてはならないのか山元の林業関係者が変わらなくてはならないのか?私はどちらも変わらなくてはならないと思います。
家の設計が出来た。「じゃ何時出来ます?3ヶ月位で出来ますか?」こういう会話がいつも出てきます。公共事業でもそうですがどうしても年度予算で物事が動いています。だから「伐採に適した時期(冬)に伐採し山で充分天然乾燥(葉枯らし)して出材して・・・」なんていってると時間ばかり掛かります。それを今の時代は許さない風潮があります。工業化が進み「家は買う物」という文化になってしまっています。何故か?自然を理解していないからです。山元の林業家の方も消費者の方も含めて今の時代は余りにも経済最優先主義がつっぱしり過ぎた為に地球上に住んでいる限り避けて通れない自然との共生が意識の遠くに追いやられてしまっています。
時間がかかる天然乾燥に代わり強制乾燥機が国の100%補助で整備され林業機械も日本では世界有数のコストを掛けて投入されています。なのに国産材は流通しない。高価な林業機械も稼動しない。これでは何の為の補助制度なのか分からなくなってしまいます。文化の無いところに機械だけ投入しても効果は得られないのです。
私は東京へ出る度に思います。今、私は森の中で木々に囲まれて暮らしています。そしてその暮らしは金銭的に豊かでなくても精神的にとても豊かに暮らす事が出来ています。勿論、人それぞれなので都会での暮らしが向いている人もいるでしょうが本来、人間は昔、自然と共に生きてきたはずです。そういうDNAが少なくても自分たちの体には残されているはずです。
林業再生にはそういう文化の見直しが絶対的に必要です。農業にも共通し全ての産業にも共通する事だと私は思います。是非、自然との共生に重きを置いた文化の再生に官民一体となった取り組みをして欲しい欲しいと思います。そうすれば島国である自然豊かな日本独自の文化を生み出すことが出来、その時こそ世界に誇れる日本文化の再生が始まると思います。
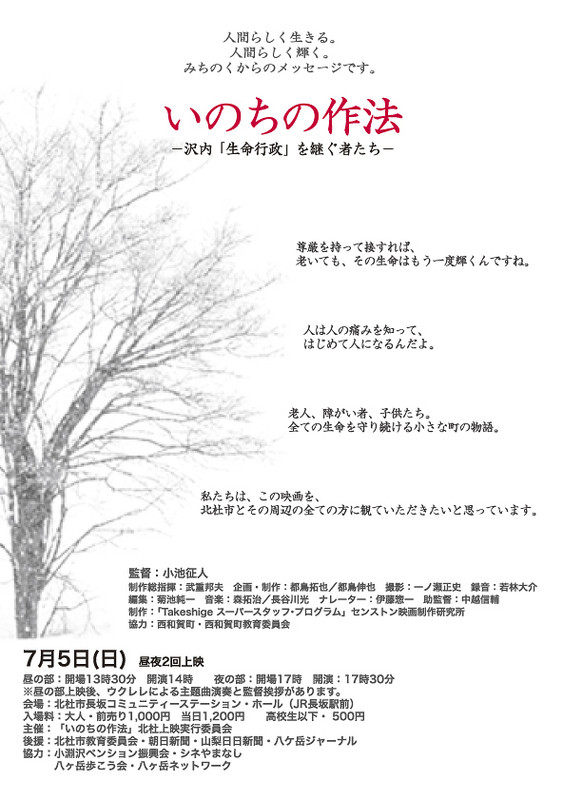
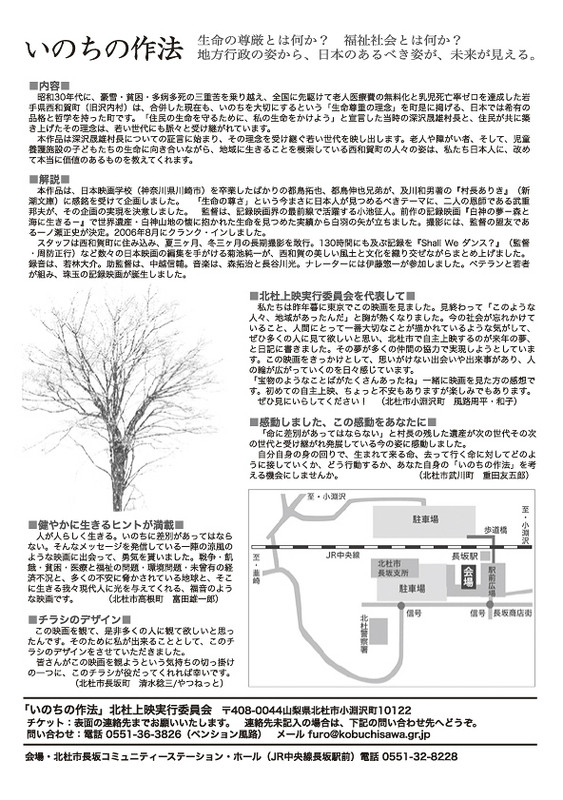










































最近のコメント