GWのひとり言
今年も私の嫌いな(笑)GWがやってきました。昨年のGWは東日本大震災の影響で自粛ムードが広がった反動で八ヶ岳には多くの観光客が集まりました。今年はどうかな?と思っていたら今のところ知り合いの地元の店の人に聞いたらさほどでも無い様な話でした。
それでも森の中には車を止めて双眼鏡を取りだして楽しそうに鳥の姿を追い求めるバードウオッチャーの姿が多く見受けられました。私なんか朝、新聞をとりに行くのに森の中の道を歩いていると見知らぬ方が道の真ん中に三脚を立てて一所懸命、鳥の姿をカメラに収めておられるので何となく近くを通るのが気の毒に思いながら小声で「おはようございます」と声をかけると向こうの方も小声で挨拶を返してくれました。
そこでフト気付きました。今更なんですが森の中で毎日過ごしている私にとっては当たり前の風景、それは小鳥の声だったり樹木が風で揺れる音だったり、新緑の美しさだったりが実は普段、都会で暮らしている人達には貴重な自然とのふれ合いの時間なんだな~と・・・私自身も20年前に都会に住めなくなって八ヶ岳に移住してきたのですが段々、こちらの生活に慣れてしまって自分達の生活を取り巻いている普段の光景が当たり前の事になってしまいましたが20年前はこの自然豊かな八ヶ岳の地に憧れてほとんど逃げるように来てしまったんだな~と言う事を思い出してしまいました。
だからこそ、この貴重な自然を大切にしていかなくてはならないのだと、本当に今更ながらGWでこちらに楽しみに来られる人達を見ていると思いました。それは住んでいる我々の務めでもあると思います。
話は変わりますが先日、ある方と話しをしている時に面白い話を聞きました。それは、ニューヨークに住んでいるその方の知人のアメリカ人が何年振りかに日本を訪れた時に日本人の印象が随分変わってしまったというのです。それは以前、日本に来た時に見た日本人の顔と比べて随分、悪くなったと言う事です。それはたまたまその方が訪れた場所の方がそうだったのか、それとも個人の感覚の違いなのか分かりませんが昨年の東日本大震災や長引く経済不況の影響も、もしかしたら有るのかも知れません。
何れにしても昨年の3/11以降明らかに何かが変わろうとしている事を私も感じています。それがもしかしたら普段、日本に住んでいる者には分からない日本人の顔の変化として海外から来られた方には感じられたのかも知れませんね。
今年、我が家のコブシの木はほとんど花を付けませんでした。コブシの花が満開になる時は暑い夏が来ると聞くので今年は以外と冷夏になるのかな何て事をコブシの木を見上げながら感じています。
変わって良いもの、変わってはいけないものがあると私は思います。変わって良いもの、それは時代の変化に伴う価値観や文化。変わってはいけないもの、それは自然を畏れ尊ぶ心。一見、相反する考えのようですが実は同じ様に考えていかなくてはならない事のように思います。
先日、新聞の記事で瀬戸内寂聴さんが原発再稼働に反対して経済産業省の前でハンガーストライキに参加された事を知りました。瀬戸内氏が生きてきた人生の中で今が日本人にとって最悪の時期だと感じておられるという記事でした。今、私達が未来の子供達に出来る事を責任を持って一歩踏み出さなくてはならない時にきっと差し掛かっているのだろうなと私も思います。何てことをGWの森の中で考えてしまいました。

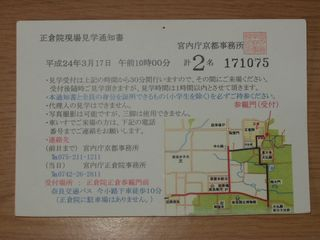









































最近のコメント